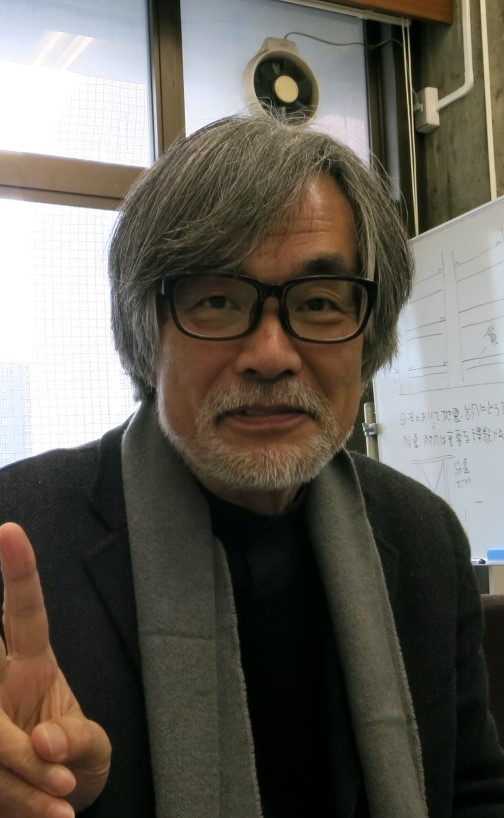- トップページ
- >
- ブログ
ブログ
blog
完璧虹
2013.12.17
先日長野県上田に行った。
上田では9月に「逆さ霧」を見ることができたけど、今度は完ぺきな虹を。

二重の虹です。
現地の方に聞いたら、上田ではよく虹が出るらしい。
やはり自然が元気なのかなー。
八勝館
2013.12.15
名古屋に八勝館という料亭があります。
料亭に出入りするような身分ではないのだが、
八勝館には建築家・堀口捨巳(ほりぐちすてみ1895-1984)が設計した「御幸の間」という将来国宝になること間違いなし、の名建築があります。
堀口捨巳は僕が最も尊敬する建築家の一人だが、
八勝館からは学ぶことが多く、高い昼飯代を奮発して何度か見学に行ったことがあります。
最近またこの八勝館に行ったのだが、今回は違った目的で、
今作っている建物の庭師に、この八勝館の庭を参考にしてもらうため。
八勝館の作庭は誰かわからないが、それなりの人の手によるものに違いない。
その庭です。

基本は苔と楓。
富士山
2013.12.03
而邸 ⅩⅣ
2013.11.26
而邸 ⅩⅢ
2013.11.22
やっぱー、ミヤコだなー。
2013.11.06
先日、第9回目の「木の建築賞」の第2次審査会が京都造形芸術大学で開かれた。
今年からこの賞の審査委員長をやっている。
審査委員長と言う役を果たしホッとしながら、
小雨の中、哲学の道の南禅寺前辺りを歩いていたら、
堂々としているが、何とも品のいい門がある。

門の足元を良く見たら、

柱の足元は雨でやられるので、
装飾を施した板で保護しているのだろう。
この板の小口(切り口)は白く塗装をしてある。
さらに板の止め方にも、大きめの鋲を装飾的に打つ工夫がしてある。
またちょっと歩みを進めたら、
こんな屋根が。

おそらく鉄筋コンクリート造に違いないが、
そう思わせないように屋根や外壁に工夫がある。
弾丸ツアー Ⅳ
2013.11.02
弾丸ツアーⅢ
2013.10.31
たった36時間のシンガポール、
ほんのチョイしか見てないわけで、どの建物が一番良かったと言える柄じゃないが、
見た中では、有名なラッフルズホテル。
コロニアルスタイルで、明治の初めのころに作られたホテル。
第二次世界大戦中は日本軍が占領していたため、
このホテルも接収され、メイドさんの服も和服だったとか。
今や想像だにできない。
この写真はラッフルズホテルの紹介でよく見かける写真だが、

スケスケの模様に光の透過がきれい。
南国らしくいろんなところにスケスケの模様が使われている。

決して白と黒で全体がまとめられているわけではないが、
白い塗装に対し、その他が落ち着いた色なので黒く見える。
そのことにより白自体の柄と、濃い隙間の模様がはっきりと映し出される。

弾丸ツアー Ⅱ
2013.10.25
シンガポールは36時間滞在だったけど、
もっと遠いベルリンにやはり同じくらいの滞在時間、という旅行もあった。
ベルリンの壁が壊されて間もない頃、
ある企業の社長が、
「泉さん、旧東ベルリンにある貴族の館を購入したいんだけど、本当にいい建物かどうか見てよ」とのことで見に行った。
この時も短時間だったけど、目的の建物以外にもたくさんの建物を見ることができた。
もっともその時印象深かったのは、第2次世界大戦の弾痕の跡がまだそこらじゅうに残っていて、
戦争の生々しさを見たこと。

次の弾丸ツアーはワールドカップドイツ大会。

このツアーはまさしく「弾丸ツアー」と銘打ったものだったけど、
この時も会場近くの街の建物をたくさん見ることができた。
ケルンの大聖堂もこの時始めてみた。
もっとも試合のほうはオーストラリアにボロ負けだったけど。

意外と短時間の海外旅行でも結構建物を見ることができる。
建築家って、本当に貧乏性。
それにしても地球は本当に小さくなった。
僕らが子供の頃、海外旅行は夢のまた夢だった。
今や、日常的に海外を行ったり来たりしている人はザラ。
何十時間、いや何時間滞在なんて当たり前になってきている。
でも僕らにとって、海外はやり新鮮な体験。
弾丸ツアー
2013.10.04

滞在時間わずか36時間だけど、このような建物がある国に行って来た。
結構有名になった建物なので皆さんもご存じかも。
シンガポールにある超高層の建物です。
3つの超高層ビルの上に船が乗っているようなデザインで、一度見たら忘れられない。
建築家はモシェ・サフディー。
このサフディーさん、最初に名前を聞いたのは僕が建築を勉強し始めた頃の大昔。
1967年のモントリオール万国博覧会で、
若くしてアビタ67と言う建築史にも残るような集合住宅を作り、超有名になった。
しかし、その後彼の名前をまったく耳にしなくなったが、4~50年ぶりに聞いたのがこのシンガポールの建物。
この建物を近くに行って見たいとは思わないが、
その後の彼の人生の変遷をも遠くから見ているようで、
感慨深い。
鈴なりの抜け殻
2013.09.30
どこの川と言わない方がいいでしょう
2013.09.15
HAKUTAKE Limited.
2013.09.04
焼酎を持参して、
打ち合わせに建て主さんが来られた。
その焼酎が何とも美しい。
最近、美しい瓶を見るがこれほどのものは滅多にない。

名前を見ると「白岳リミテッド」とある。
「白岳」は聞いたことのある名前。
僕が育った町を流れる川の上流、人吉市の酒蔵。
「しろ」と言う焼酎で有名。
この焼酎がマイルドで美味しい。
絶品と言ってもいいくらい。
焼酎は芋か麦か米から作るのが一般的だが、
この焼酎の原材料はナツメヤシと書いてある。
ロシアでは革靴からウウォカを作ることもある、と読んだことがあるから、
ナツメヤシということはあるにちがいない。
それにしても美味しい。
美味しいから、アッというまに減っていく。
半分くらいになったところで、
この瓶を建て主さんと良く見たら、瓶の中にまた瓶がある。

なんでだろう? 理由がよくわからない、不思議?
ちょっと飲み過ぎの打ち合わせだったけど、
いい建物になること間違いなし。
滝のような雲
2013.08.31
板金屋に乾杯
2013.08.20
August 16, 2013
2013.08.16